|
|
|
 |
 |
和泉流には、現行曲(レパートリー)と定められた狂言が254曲あります。(※新作狂言は含まれません)
ここでは、254曲全曲のあらあらのあらすじと、オススメとしてピックアップした曲に関しての詳しい解説を
ご覧いただけます。皆様の鑑賞の手引きにお使いくださいませ☆
また、「これが見たい」「あの時見た曲はどれだったのだろう?」という疑問にもメールでお答えします。
ぜひ、ご活用下さい。 |
|
 |
|
 |
 |
胼(あかがり)
太郎冠者は、足にあかぎれがきれているのを口実に、主人に背負われて川を渡りかけるが・・・。

芥川(あくたがわ)
生田八幡の遷宮に参詣する二人の身体障害者が、お互いの欠点を歌に詠みこんで暴露しあう。

悪太郎(あくたろう)
大酒のみの悪太郎が、酔いつぶれて道に寝込んだところ、夢の告げと称した伯父の諫めによって出家する。

悪坊(あくぼう)
六角堂の悪坊と称する乱暴者が、道連れになった出家によって改心し、仏道修行に出る。

朝比奈(あさいな)
冥土へ向かう途中で閻魔王に出会った朝比奈三郎が、戦の手柄話を聞かせて、閻魔王に極楽への導きをさせる。

麻生(あそう)
元日の用意を命じられた二人の召使、藤六と源六が、主の宿所を忘れて囃子物でたずね歩く。曲中、髷を結う特殊な狂言。

合柿(あわせがき)
渋柿を甘いといって売りつける柿売りが、逆に試食をさせられて渋っ面をかく。

粟田口(あわたぐち)
粟田口が刀の銘とは知らぬ大名が、太郎冠者が連れ帰った粟田口と自称するすっぱに翻弄される。

庵の梅(いおりのうめ)
老尼の住む庵を訪ねた女たち。ともに早春のひと時を、酒を酌み交わし、舞い謡う、登場人物が女性だけの狂言。

井杭(いぐい)
かぶると姿が見えなくなる不思議な頭巾を手に入れた井杭が、自分を探そうとする知人と易者を翻弄する。

石神(いしがみ)
離婚を迫る妻の先回りをして石神になりすました男が、神楽を舞う妻に、正体を見破られる。

因幡堂(いなばどう)
大酒のみの妻に嫌気がさした男が、因幡堂にこもって新しい妻を得ようとするが、その新しい妻とは・・・?

犬山伏(いぬやまぶし)
口論する山伏と僧侶が、茶屋の仲裁で人食い犬を祈り鎮めたほうを勝者としようとする。結果は・・・。

今神明(いまじんめい)
宇治明神へ出店を出して茶を商う夫婦者。しかし、慣れない商売に、客もつかず、店をたたんで都へ帰る。

今参(いままいり)
召抱えた新参の者を相手に、秀句(洒落)問答を楽しむ大名。

伊文字(いもじ)
妻乞いをした主人が、歌で詠まれた女の住所を忘れてしまい、歌関を設けて通行人を止めてたずねることにする。

入間川(いるまがわ)
本国へ帰る途中、入間川にさしかかった大名が、入間様という逆言葉を使って入間の何某と問答をするが・・・。

伊呂波(いろは)
寺子屋へ手習いにあげる子のために、事前に「いろは」を教える親と子の珍問答。

岩橋(いわはし)
結婚後10日も衣をかぶって顔を見せず、ものも言わない新妻に、仲人から歌を詠めば打ち解けられると教えられて・・・。

魚説法(うおぜっぽう)
お経も知らない見習い僧が、頼まれて法事に出かけ、魚の名を並べた生臭説法を始める。

鶯(うぐいす)
うぐいすを寵愛する稚児のために、野へ出て野鳥でも刺そうとする家人が、持ち主のあるうぐいすを欲しさに太刀も刀も取られてしまう。

牛盗人(うしぬすびと)
法皇の使う牛を盗んだ男が、わが子の訴えで捕えられるが、その子の才覚で放免される。

歌争(うたあらそい)
早春の野へ遊びに出た二人連れが、古歌の読み違いをめぐって、口論のはてに相撲で勝負をつけようとする。

内沙汰(うちさた)
口下手な百姓右近(うこ)が、裁判の下稽古をするうちに妻になじられた口惜しさから、妻が仲間の百姓左近(さこ)と通じていることをあばく。

靱猿(うつぼざる)
狩りに出た大名は、通りすがりの猿曳がつれている小猿を見て、靱に張るから皮を貸せとせまる。が、猿曳の愁嘆を見て命を助け、猿唄に舞う猿とともに戯れる。 < 詳細解説 >

瓜盗人(うりぬすびと)
盗みに入った畑の案山子を相手に、祇園祭の余興に出す鬼の責めの稽古をする瓜盗人。しかしその案山子は・・・。

右流左止(うるさし)
塩飽の藤造という男が、茶屋の女を相手に「うるさし」についての語源争い。和泉流宗家の専有曲。

越後聟(えちごむこ)
聟入りの芸を披露する中で、聟が特技として越後の獅子舞を舞う。和泉流宗家の専有曲。

夷大黒(えびすだいこく)
河内の国の有徳人が家に夷と大黒を勧請すると、その信仰の深さをめでて夷と大黒は宝を与え、その家の福神に納まる。

夷毘沙門(えびすびしゃもん)
美人のひとり娘の婿に志願する夷と毘沙門の争い。結局、二人そろって舅の家の福神におさまる。

大藤内(おおとうない)
工藤祐経の身近に使える神職の大藤内が、曾我兄弟の討ち入りにおびえる。能「夜討曾我」の替間狂言。

岡太夫(おかだゆう)
舅の家で食べたわらび餅の名を忘れた夫が、妻に「和漢朗詠集」を吟じさせ、やっと思い出す。

鬼瓦(おにがわら)
久しく在京の大名が帰郷するにあたって、因幡堂の薬師如来へ参詣する途中、鬼瓦を見て国もとの妻を思い出す。

鬼の継子(おにのままこ)
子どもを抱いて夜道を行く女の前に鬼が現れ、妻になって地獄へ来いと口説く。本性を現した鬼は子どもを食べようとする・・・。

鬼丸(おにまる)
鈴鹿山に住む山賊、鬼丸が、観音の化身である旅の僧にさとされて改心し、仏道に帰依する。

伯母ヶ酒(おばがさけ)
鬼に化けて、ケチな酒屋の伯母を脅し、したたか酒を飲んだ甥が、酔いつぶれて正体を見破られる。

お冷し(おひやし)
盛夏、清水へ涼みに行く主従が、滝の水を汲むことから、水を「お冷し」といういわれについて争う。

折紙聟(おりがみむこ)
舅からの引き出物がないのに腹を立てた聟が離縁しようとすると、妻は刀一振りと銭百貫の目録を見せて、もとのさやにおさまる。

音曲聟(おんぎょくむこ)
聟は、いたずらな知人に教えてくれた通り、謡を謡いながら挨拶を始める・・・。

懐中聟(かいちゅうむこ)
出される物はすべて懐中に入れよと、いたずらな知人に教えられた聟が、引き出物の弓を左右の袖に通し、不自然な姿で祝言の舞を舞う。

鏡男(かがみおとこ)
越後の国、松の山家の男が、都のみやげに鏡を買って帰るが、初めて鏡を見た妻は、女を連れてきたと怒り出す。

柿山伏(かきやまぶし)
道中、のどが渇いた山伏が、柿の木に登って柿をほおばるところへ畑主が現れて、犬だ、猿だ、鳶だと、鳴きまねをさせて山伏をからかう。

蝸牛(かぎゅう)
主人の言いつけで、長寿の薬になるというカタツムリを探しに来た太郎冠者は、竹やぶに寝ている山伏をカタツムリと思い込み・・・。

隠狸(かくしだぬき)
太郎冠者が狸を獲るという噂を聞いた主人は、狸汁を作って客を呼ぼうと、太郎冠者に真偽を確かめるが・・・。

角水(かくすい)
「角水」の課題にこたえて上手に歌を詠んだ者を聟に迎えようという掲示を見た、三人の男たちは・・・。

蚊相撲(かずもう)
太郎冠者が連れて帰った新参の者が、実は江州坂本の蚊の精だとも知らず、大名は相撲を取り、刺されて失神・・・。

歌仙(かせん)
玉津島明神の絵馬から抜け出した六歌仙が題詠をはじめるうちに、小野小町をめぐって人丸と僧正が争う。夜明け鳥の声に、もとの絵馬に戻る。

勝栗(かちぐり)
大和の百姓と津の国の百姓が、年貢を納めるために上京。大和柿と勝栗を領主の蔵に納め、めでたい歌を詠む。

金岡(かなおか)
御殿で見そめた美しい上臈のおもかげが忘れられぬ絵師、金岡の狂乱。妻は嫉妬に怒り、自分の顔を恋しい人の顔に似せて彩色せよと迫るが・・・。

金津地蔵(かなずじぞう)
わが子を地蔵に仕立てて金津の男に売りつけた親が、在所一同、踊り念仏に浮かれる間にわが子を取り戻す。

蟹山伏(かにやまぶし)
山の中で、蟹の精に出くわした山伏と強力は、行力の甲斐もなく、耳をはさまれ散々に痛めつけられる。

鐘の音(かねのね)
黄金づくりの太刀を作るから鎌倉へ行き「金の値」を訊いてこいと命じられた太郎冠者が、鎌倉の寺々をめぐり「鐘の音」を聴いてくる・・・。

鎌腹(かまばら)
山へ働きに行けと、妻に棒や鎌でおどされた夫が、無念さに鎌で切腹しようとするが、どうにも死にきれない・・・。

雷(かみなり)
都落ちをした藪医者武蔵野の原へさしかかると、にわかに落雷。腰を打った雷は藪医者の治療を受けて、ふたたび昇天する。

川上(かわかみ)
盲目の夫は、川上の地蔵に参篭した甲斐あって目があくが、地蔵のお告げは「連れ添う妻は悪縁ゆえ離縁せよ」と条件をつける。しかし二人は別れられず、夫は再び盲目に。

河原太郎(かわらたろう)
妻が市で商う酒屋へ飲みに来て、商売の邪魔をする夫。妻は腹をたて、大酒を飲ませて報復する。

鴈雁金(がんかりがね)
津の国の百姓と和泉の国の百姓が、領主の館で、年貢物について「がん」か「かりがね」かと言い争う。

雁大名(がんだいみょう)
振舞いの肴が買えないので、一計を案じ市場で喧嘩をよそおい、どさくさにまぎれて雁を盗む大名と太郎冠者。

雁礫(がんつぶて)
大名が弓で雁を狙うところを、通りがかりの男が石つぶてで仕留めてしまう。大名は自分の獲物だと言い張るが・・・。

菊の花(きくのはな)
主人に無断で都見物をしてきた太郎冠者が、祇園の花見の様子を身ぶりおもしろく主人に話して聞かせる。

狐塚(きつねづか)
狐塚の田へ鳥追いに行った太郎冠者が、慰労に来た主人と次郎冠者を狐と思いこみ、しばりあげてしまう。

牛馬(ぎゅうば)
市場で先着争いをする牛商人と博労(ばくろう)。それぞれの優秀さを主張して、市司の権利を得ようとする。

清水座頭(きよみずざとう)
互いに盲目ながら良き配偶者を求めて、清水の観世音に参篭した座頭と瞽女(ごぜ)が、夢の告げで結ばれる。

木六駄(きろくだ)
奥丹波から都まで、雪の降りしきる中を主命で12頭の牛を追ってゆく太郎冠者。途中、老の坂の峠で一休み、土産に持参の酒樽に手をつけて・・・。 < 詳細解説 >

禁野(きんや)
禁野(禁猟区)へ出かけた大名が、見とがめた男に弓矢を取られた上に、身ぐるみはがれ、後悔の念を物語る。

杭か人か(くいかひとか)
主人の留守に夜回りに出た臆病者の太郎冠者。人影を見て「杭か人か」と尋ねる。

茸(くさびら)
庭に不気味なキノコが生えてきたので、山伏に頼んで退治してもらおうとするが、山伏が祈れば祈るほど、キノコは増えるばかり・・・。

鬮罪人(くじざいにん)
祇園祭の山車に地獄の鬼の責めを出すにあたり、くじを引くと主人は罪人、太郎冠者は鬼という皮肉な役回り。稽古の中で日ごろの鬱憤を晴らす。

口真似(くちまね)
酒ぐせの悪い客を適当にあしらい帰すために、主人は太郎冠者に、自分の言うようにしろと命じると、太郎冠者は主人の真似をして・・・。

口真似聟(くちまねむこ)
何事も舅の口真似をしていればよいと教えられた、愚鈍な聟の失敗談。

首引(くびひき)
鎮西八郎為朝と、姫鬼の力くらべ。親鬼は姫鬼の勝ちを願って、小鬼たちに加勢させる。

蜘盗人(くもぬすびと)
連歌の会を催す家へ忍び込んだ盗人が、蜘蛛の巣にかかって捕えられる、風雅のセンスを発揮して・・・。

鞍馬参(くらままいり)
太郎冠者か鞍馬の多聞天からさずかった福ありの実(梨)を、主人は拍子にかかって受け取ろうとする。

鞍馬聟(くらまむこ)
姉娘の夫である鞍馬の聟と妹娘の聟である京の聟が舅の家で初対面。ところが、材木商の鞍馬聟が、かつて商売上喧嘩をした相手が京の聟だった。あわてた鞍馬の聟は・・・。

栗焼(くりやき)
丹波から届いた栗を、主人の言いつけで焼き上げた太郎冠者は、試食のつもりが全部食べつくしてしまう。その言い訳は・・・。

鶏猫(けいみょう)
「牛盗人」と同じ構想。牛が猫に替わる。和泉流宗家の専有曲。

鶏流(けいりゅう)
早暁、一番鶏が歌ったら起こせと主人から言いつけられていた太郎冠者。油断して寝過ごした苦しまぎれの言い訳に、鶏は「鳴く」もので「歌う」ものではないと言い張り、古歌を引き合いに主人と論争。

柑子(こうじ)
前夜の酒席で出た土産の柑子を主人から預かった太郎冠者。食べてしまった口実を、長々と物語る。

柑子俵(こうじだわら)
約束の柑子をよそへ又売りしてしまった山家の男が、柑子の代わりにわが子を鬼の姿につくって俵に入れ売りつける・・・。

膏薬練(こうやくねり)
鎌倉の膏薬練と上方の膏薬練が道で出会い、互いの系図を争い、吸出し膏の効力を競い合う。都の公家政権と鎌倉の新興武家政権の対立を風刺している。

小傘(こがらかさ)
ばくちで食いつめて、にわか坊主となった主従。田舎者から法事を頼まれ、はやり歌をお経めかして唱え、施物をまきあげて逃げ去る。

腰祈(こしいのり)
修行を終えて帰郷した若い山伏が、孝行に祖父の曲がった腰を伸ばしてやろうと懸命に祈るが、祖父の腰は伸びすぎて・・・。

子盗人(こぬすびと)
盗みに入った家の座敷で、寝ている赤ん坊を見つけ、その愛らしさに、盗みに入ったことも忘れて、あやして戯れる人の善い盗人。

木実争(このみあらそい)
春のひと時、花見をしていた橘の精一族と茄子の精一族が、和歌の争いから乱闘になるが、嵐に見舞われ、あまりの寒さにそれぞれの棲みかに退散する。

昆布売(こぶうり)
供も連れずに北野天満宮の御手洗祭に出た大名が、通りがかりの昆布売に太刀を持たせるが、逆に太刀で脅されさまざまな音曲で昆布を売らされる。

昆布柿(こぶがき)
淡路の百姓は柿を、丹波の百姓は昆布を、領主の蔵へ納め、問われるままにめいめいの珍妙な名前を、リズムに乗せて答える。

賽の目(さいのめ)
算勘にたけた者を聟に求めるという高札を見て、三人の男が次々にやってくるが、500個のサイコロの目の合計はいくつかと尋ねられて・・・。

才宝(さいほう)
才宝という名の老人の三人の孫が揃って訪ね、長寿にあやかって名をつけてくれと頼む。それぞれに面白く命名した才宝は、孫たちの手車に乗って浮かれる。

酒講式(さけのこうしき)
酒癖の悪い手習いの師匠に、親たちは講義するが、師匠は居直って酒の徳を説いて聞かせながら泥酔する。腹を立てた親たちは・・・。

咲嘩(さっか)
主人に、都の伯父を連れて来いと言いつけられた太郎冠者は、間違えて見乞の咲嘩(みごいのさっか)と称する都のすっぱを連れて帰る。その接待の結末は?

薩摩守(さつまのかみ)
船賃を持たないで神崎の渡しにさしかかった僧が、茶屋の亭主に教えられて、秀句好きの船頭につけこんでただ乗りをしようとする。

佐渡狐(さどぎつね)
年貢を納めに上京の途中、道連れになった越後の国の百姓と佐渡の国の百姓が、佐渡に狐がいるかいないかで口論する。領主の館に着き、代官に裁定をあおぐが・・・。

猿座頭(さるざとう)
美人の妻を連れて花見に出かけた座頭。おりから通りかかった猿曳が、匂当の妻を誘惑し、身代わりに猿を置いて逃げ去る。

猿聟(さるむこ)
三吉野の聟猿が供をつれ、嵐山の舅猿のもとへ聟入りする。キャアキャアという猿言葉で終始する珍しい狂言。

三人片輪(さんにんかたわ)
身障者を召抱えようという有徳人の家に、盲目・いざり・唖をよそおった、三人の食い詰めたばくち打ちが集まる。

三人長者(さんにんちょうじゃ)
近江、大和、河内の国の三人の長者が、長者号を拝領して帰国の途中に出会い、それぞれ富貴になったいわれを物語る。

三人夫(さんにんぶ)
美濃、淡路、尾張の国の百姓が、揃って年貢を納め、一首の歌を三人で詠み、褒美に万雑公事を許されて、帰国する。

三本柱(さんぼんばしら)
金蔵を建てるについて、三本の柱を、一人が二本ずつ持って運べと知恵を試された太郎冠者・次郎冠者・三郎冠者。

磁石(じしゃく)
大津松本の市で人売りに出会った男は、人買い宿に連れこまれるが、売られたことに気付き逃走。追ってきた人売りに、自分は磁石の精だと言って逆襲する。

二千石(じせんせき)
太郎冠者が都で覚えてきた「二千石」の謡を聞いた主人は、怒って、その謡の大切な由来を物語る。

地蔵舞(じぞうまい)
よそ者を泊めてはならぬという宿屋に笠だけを預かってもらい、自分はその笠に宿を借りたと言い抜ける旅僧。亭主と酒宴になり、地蔵舞を舞う。

止動方角(しどうほうがく)
伯父に借りた馬は咳払いをすると暴れだす妙な癖がある。日頃の鬱憤晴らしに太郎冠者が咳払いをすると、主人は落馬してしまう。

痺(しびり)
使いに行けと命じられた太郎冠者は、親から譲り受けたしびれが切れたと言って、使いに行くことを拒む。

清水(しみず)
茶の水を汲んで来いと言いつけられた太郎冠者は、清水に鬼が出たと偽る。いぶかった主人が清水へ行くと、太郎冠者が鬼の面をつけて現れる。

舎弟(しゃてい)
兄から日ごろ「舎弟、舎弟」と呼ばれるが意味のわからぬ弟は、人にからかわれて「盗人」の別名だと教えられ、兄と喧嘩になる。

重喜(じゅうき)
頭を剃るよう師匠に命じられた重喜は、師の影を踏むまいと、長い柄をつけた剃刀を扱ううちに、誤って師匠の鼻をそぎ落としてしまう。

秀句傘(しゅうくがらかさ)
秀句を習おうと、秀句の得意な新参者を召抱えた大名は、その者の言葉をすべて秀句だと思い込み、太刀・刀・衣服まで褒美に与えてしまう。

宗論(しゅうろん)
浄土僧と法華僧が珍妙な教義問答を交わし、念仏合戦に浮かれるうち、気がつくと名号と題目を取り違えていた。翻然として二人は弥陀も法華も隔てのないことを悟る。

拄杖(しゅじょう)
旅僧から拄杖の注文を受けた細工屋は、一念発起して弟子入りを志し、剃髪してしまう。怒った妻は旅僧を投げ飛ばす。

真奪(しんばい)
立花の真を探しに出た主従は、途中、真を持っている男と出会い、強引に奪い取るが、かわりに太刀を取られてしまう。

末広かり(すえひろがり)
末広がりを扇と知らぬ太郎冠者は、騙されて傘を買って帰り、大名から末広がりのいわれを聞かされ追い出されるが、都で覚えてきた囃子物を謡って和解する。

素袍落(すおうおとし)
主人の伯父のもとへ、伊勢参宮の誘いに行った太郎冠者は、ふるまい酒に酔い、餞別に素襖をもらって上機嫌で帰るところを主人に見つけられ・・・。

双六(すごろく)
旅僧の回向で現れた博奕打ち、九郎蔵の霊が、双六のいわれを語って聞かせる。

鱸包丁(すずきぼうちょう)
鯉の調達ができなかった甥は、伯父に嘘の言い訳をする。見抜いた伯父は、鱸を食べさせてやろうといって、話だけの馳走をする。

酢薑(すはじかみ)
津の国のはじかみ(しょうが)売りと和泉の国の酢売りが道連れになり、それぞれの系図自慢。はじかみの「カラ」と酢の「ス」を織りこんだ洒落の応酬を繰り広げる。

墨塗(すみぬり)
本国へ帰る大名に、別れが辛いと泣き真似をする京の女に腹を立てた太郎冠者は、女が目に塗っている水を、墨に取りかえておく・・・。

政頼(せいらい)
閻魔大王は六道の辻で鷹匠の政頼に出会い、鬼たちを使って鷹狩りをさせ、獲物の雉子を食い、政頼を三年間娑婆へ帰してやる。

節分(せつぶん)
節分の夜、蓬莱の島から日本へ渡ってきた鬼が、美女に心を奪われ、小唄まじりに口説くが、宝を取られて最後は「鬼は外」。

蝉(せみ)
信州上松で、松の枝にかかった短冊の歌を見た旅僧が、回向をしていると、蝉の亡霊が現れ、死の苦しみを物語る。

煎物(せんじもの)
祇園会の囃子物の稽古に便乗して、売り声を上げる煎じ物売り。

宗八(そうはち)
元料理人のにわか出家と、元出家のにわか料理人が、同じ家に召抱えられ、互いの本職を教え合う。

空腕(そらうで)
淀へ使いを言いつけられた臆病な太郎冠者は、夜道で物影におびえて逃げ帰り、大勢の盗賊に出会って戦ったと得意満面で主人に話すが・・・。

太鼓負(たいこおい)
にぎにぎしい祇園会の行列の先頭で大太鼓を背負う、気弱な夫の晴れ姿を見て、妻は誇らしく思う。

大黒連歌(だいこくれんが)
比叡山三面の大黒天の神前。二人の参詣人が連歌を詠むと、大黒が出現し、それぞれに槌と袋を授ける。

太子手鉾(たいしのてぼこ)
太郎冠者の家にある「太子の手鉾」とは、雨漏りを防ぐ槍のこと。その意味は「もりやをとめる」という洒落。

大般若(だいはんにゃ)
檀家で出くわした僧と巫女が、たがいに読経と神楽で競うが、巫女の色香に見ほれた僧は、神楽に興じてしまう。

田植(たうえ)
賀茂神社の御田植行事に、神主は早乙女たちを呼び出して、にぎやかに謡いの掛け合いで、田を植えてゆく。

宝の笠(たからのかさ)
宝くらべに必要な宝物を買いにやらされた太郎冠者は、蓬莱の島の鬼が持っていた隠れ笠だといって古笠を売りつけられる。

宝の槌(たからのつち)
宝くらべに必要な宝物を買いにやらされた太郎冠者は、望みの物を何でも打ち出せる小槌だといって、太鼓の撥を売りつけられる。

竹の子(たけのこ)
隣同士の畑主と藪主が、竹の子の所有を争うが、仲裁人が入り、相撲の勝負で決着をつけることになる。

蛸(たこ)
播磨の国・清水の浦で、旅僧の前に現れた大蛸の亡霊が、漁師たちに食べられてしまった無念さを物語る。

太刀奪(たちばい)
北野天神に詣でる途中、通行人の太刀に目をつけ、奪おうと思った太郎冠者が、逆に主人の刀を奪われてしまう。

狸腹鼓(たぬきのはらつづみ)
猟師に狸を獲ることを思いとどまらせようと老尼に化けた古狸が、正体を見破られると、命乞いをして、腹鼓を打つ。宗家一子相伝の曲。

樽聟(たるむこ)
聟入りに、祝儀の酒樽を持って同行した男が聟と間違えられ、盃ごとをする。無視された聟は腹を立て、引き出物の太刀を取って逃げる。

千切木(ちぎりき)
連歌仲間に愚弄された気の弱い夫をけしかけて、講中の家々に夫ともども怒鳴りこむ気丈な妻。

竹生島参(ちくぶしままいり)
主人に無断で竹生島参りをしてきた太郎冠者は、みやげ話に、竜、犬、猿、蛙、蛇にまつわる秀句を聞かせるが・・・。

児流鏑馬(ちごやぶさめ)
流鏑馬の神事で、稚児の扮装をさせられた妻は、無事に行事が終わっても盃の交換ができず、ついに女と見破られてしまう。

千鳥(ちどり)
借金のたまっている酒屋に、祭に入用な酒を買いに行かされた太郎冠者は、津島祭や流鏑馬の話しで酒屋を油断させ、酒樽を持ち去る。

茶子塩梅(ちゃすあんばい)
日本人の妻と結婚した中国人の夫が、母国に残した妻を恋しがるので、腹を立てた日本人の妻は・・・。

茶壷(ちゃつぼ)
酒によって道に寝込んでしまった男の茶壷にすっぱが目をつけ、その所有を争うが、仲裁に入った代官が持ち去ってしまう。

通円(つうえん)
茶坊主・通円の亡霊が、旅僧の回向で現れ、宇治橋の供養に茶を点て過ぎて死んだ時の模様を物語る。

筑紫奥(つくしのおく)
筑紫の奥の百姓と丹波の百姓が年貢の品を納めて、所有する田の広さを笑いで表せと命じられる・・・。

筒竹筒(つつささえ)
大和の酒屋と河内の酒屋が、酒器の名と「筒」か「竹筒」かと争っていると、鳩の神が出現し、双方とも同じ意味だと説き、松尾大明神の威徳を語る。

苞山伏(つとやまぶし)
山中に寝ていたきこりと山伏。きこりの飯苞を通りがかりの男が食べて、素知らぬ顔。犯人を山伏の行力で祈り出す。

釣狐(つりぎつね)
猟師に狐を釣ることを思いとどまらせるため、猟師の伯父の白蔵主に化けた古狐。首尾よく納得させて帰る途中、餌の誘惑に勝てず、正体を現す・・・。 < 詳細解説 >

釣針(つりばり)
大和の酒屋と河内の酒屋が、酒器の名と「筒」か「竹筒」かと争っていると、鳩の神が出現し、双方とも同じ意味だと説き、松尾大明神の威徳を語る。

弦師(つるし)
大和の酒屋と河内の酒屋が、酒器の名と「筒」か「竹筒」かと争っていると、鳩の神が出現し、双方とも同じ意味だと説き、松尾大明神の威徳を語る。

唐人子宝(とうじんこだから)
大和の酒屋と河内の酒屋が、酒器の名と「筒」か「竹筒」かと争っていると、鳩の神が出現し、双方とも同じ意味だと説き、松尾大明神の威徳を語る。

唐人相撲(とうじんずもう)
中国へ渡った日本の相撲取りが、帰国の名残に宮殿で大勢の臣下と相撲を取り、最後に帝王と手合わせをする。

野老(ところ)
野瀬の郡で、旅僧の回向に現れた野老(山いも)の精が、掘り起こされ村人に食べられた最期の苦患を物語る。

とちはくれ(どちはぐれ)
斎(食事)の出る檀家と布施(お金)の出る檀家の、どちらへ行こうかと迷ううちに遅刻した出家が、双方からなじられる。

飛越(とびこえ)
寺の茶会に招かれた男についてきた新発意は、小川を飛び越えられず、川にはまって濡れ鼠になる。

丼礑(どぶかっちり)
匂当が供の座頭を連れて川にさしかかり、石を投げて浅瀬を探る。この様子を見たいたずら者が、座頭に背負われて川を渡ってしまう。

吃り(どもり)
勝気で口数の多い妻にののしられる吃りの夫は、謡がかりで抗弁するが、逆に妻の怒りを買ってしまう。

鈍根草(どんごんぞう)
鞍馬へ参詣した主従。利根草の蓼(たで)を食べた主人が太刀を置き忘れ、鈍根草の茗荷を食べた太郎冠者がそれを拾い、鈍根草のいわれを主人に語って聞かせる。

鈍太郎(どんたろう)
三年ぶりに帰国した鈍太郎を、下京の本妻と上京の愛人が奪い合うが、鈍太郎は双方に条件をつけて和解させ、二人の手車に乗って意気揚々と帰る。

長光(ながみつ)
大津松本の市に現れたすっぱは、田舎者の持っている長光の太刀を自分のものだと言い張るが、代官の機転で見破られてしまう。

泣尼(なきあま)
説教の下手な僧が泣き役の老尼をやとって連れてゆくが、老尼は寝込んでしまって役に立たず、そのくせ報酬だけは要求するので、僧は怒って拒絶する。

長刀応答(なぎなたあしらい)
適当に応答する意の「長刀応答」を取り違えた太郎冠者は、本物の長刀を振り回して花見に来た客を驚かす。

名取川(なとりがわ)
物覚えの悪い僧が、衣の袖に書いた自分の名前を、川にはまって流してしまう。川の名は名取川・・・。

鍋八撥(なべやつばち)
鞨鼓売りと浅鍋売りが、新市のリーダーの座を争って、めいめいの商売物を使って技くらべをするが・・・。

腥物(なまぐさもの)
伯父に借りた太刀を返しに行く道中が危ないので、わら苞に包んで腥物のように見せかけるが、愚かな太郎冠者はやはり奪われてしまう。

成上り(なりあがり)
参籠中、太刀を青竹にすり替えられた太郎冠者は、主人への言い訳に、成上りの故事を語ってごまかそうとする。

業平餅(なりひらもち)
空腹に耐えかねた在原業平が、街道の餅屋で餅を盗み食いする。見とがめた餅屋の主人は、餅代の代わりに娘を貰ってくれと迫る。

鳴子(なるこ)
稲の獲り入れの前に、野鳥を見張って山田の鳴子を引きながら、太郎・次郎冠者は、主人の見舞いの酒を飲んで、曳く物尽くしや名所尽くしを謡いつつ、寝込んでしまう。

鳴子遣子(なるこやるこ)
鞍馬へ参詣に来た二人の男は、鳥追いの道具を「鳴子」か「遣子」かと刀を賭けて言い争うと、茶屋が仲裁に入り・・・。

縄綯(なわない)
博奕のかたに取られてよそへ奉公に行った太郎冠者は、もとの家に帰って、縄を綯いながら、先方の家庭の悪口を主人に聞かせるが・・・。

仁王(におう)
食いつめた博奕打ちが、友人の入れ知恵で、上野に降臨した仁王に化けて、参詣人から供物をまきあげる。

二九十八(にくじゅうはち)
清水の観世音に妻乞いをした男の前に現れた女は、住所を問われると春日の里・室町の角から「にく」と答えて立ち去る。男が18軒目を訪ねると、女はいたが・・・。

若市(にゃくいち)
尼僧・若市が花を携えて里帰りするのを住持が見とがめ侮辱するので、腹を立てた若市は仲間の尼たちを語らって、長道具で住持に逆襲する。

鶏聟(にわとりむこ)
聟入りの作法を知らぬ聟は、いたずらな知人の教えるままに、烏帽子を前折りに冠り鶏のトサカに似せ、鶏の鳴きまねや蹴合うまねをする。 < 詳細解説 >

ぬけから(ぬけがら)
使いに出る前に酒をふるまわれる癖のついた太郎冠者が、泥酔して道に寝込んでいるのを見て、主人は鬼の面をかぶせておく。目覚めた太郎冠者は自分が鬼になったと思い込み・・・。

塗師平六(ぬしへいろく)
都の塗師(漆細工の職人)が、越前の国に住む弟子の平六を頼って下ってくる。師匠がいては夫の商売の妨げと思った平六の妻は、夫は去年死んだと嘘をつく。

塗附(ぬりつけ)
大晦日、塗師に出会った二人の大名は、年始に着用する烏帽子を路上で塗り直させる。が、乾かすうちに二人の烏帽子はくっついて離れない・・・。

寝音曲(ねおんぎょく)
主人に謡をリクエストされた太郎冠者は、今後たびたび謡わされてはかなわないと思い、酒を飲まねば声が出ない、妻の膝枕でなければ謡えないなどと、勿体をつける。

禰宜山伏(ねぎやまぶし)
道中で出会った神主と山伏が口論を始め、茶屋の仲裁で大黒天を祈って影向(ようごう)したほうを勝者にしようと、互いに祈りくらべをする。

萩大名(はぎだいみょう)
清水坂の茶屋に萩の花見に出かけた無風流な田舎大名。太郎冠者は気をきかせて、茶屋の亭主に即興の和歌を所望された場合を予想して、いろいろに予習しておくのだが・・・。

博奕十王(ばくちじゅうおう)
子鬼どもを従えて六道の辻まで出向いた閻魔大王と、地獄に落ちてきた博奕打ちとのサイコロを振っての勝負。無一物になった閻魔大王は博奕打ちを極楽に案内させられる。

伯養(はくよう)
座頭の伯養は主人の言いつけで、ある邸に琵琶を借りに行くが、同じく琵琶を借りに来た匂当と出くわし、先着争いになる。歌を詠み相撲を取って勝負をつけるが・・・。

馬口労(ばくろう)
六道の辻で罪人を待ち受ける閻魔大王の前に現れたのは馬喰。閻魔は乗馬の稽古をつけてもらうつもりが、轡をはめ手綱を締められ、極楽への道案内をさせられる。

八句連歌(はちくれんが)
借金延滞の言い訳に行った男が、居留守を使われ連歌を詠み残して帰ろうとすると、その心を感じた貸主は連歌の付け合いをして借状を返してやる。

鉢叩(はちたたき)
茶筅を売って渡世を営む大勢の鉢叩僧が、北野天神に参詣し、神前で踊りながら空也念仏を合唱する。

花争(はなあらそい)
花見に行こうという主と、その言葉を聞きとがめた太郎冠者が、「花」というか「桜」というかで言葉争い。互いに古歌の例を引き合いに出して・・・。

花折(はなおり)
住持は新発意に留守を言いつけ、花見禁制を申し渡して出かけるが、大勢の花見客が押しかけると断りきれず、招じ入れてともに酒宴を催してしまう。

花子(はなご)
妻には、持仏堂に篭り坐禅すると偽り、太郎冠者を身代わりに仕立てた後、愛人・花子との逢瀬を楽しんだ男。朝帰りして、坐禅衾の中に妻が入れ替わっているとも知らず、一夜の様子を話しだす。

鼻取相撲(はなとりずもう)
新参者と相撲を取り、鼻をつかまれて失神した大名は、土器(かわらけ)で鼻をおおい再び挑戦するが。

花盗人(はなぬすびと)
夜中に庭の桜の花を盗まれた主人が番をしていると、昨夜の花盗人が現れたので捕えて縄をかけるが、古歌を詠ずる優しさに免じ、罪を許す。

不腹立(はらたてず)
名を問われて、ふと出まかせに「腹立てずの正直坊」と名乗った旅僧は、さんざんに愚弄され、ついに堪忍袋の緒が切れる。

張蛸(はりだこ)
正月の引き出物に張蛸を買ってこいと言いつけられた太郎冠者は、都のすっぱにだまされ、張太鼓を売りつけられる。

比丘貞(びくさだ)
ある男が成人した一人息子を連れて、知合いの老尼に烏帽子親になってくれと頼む。老尼は庵太郎比丘貞と命名して引き出物を贈り、乞われるままにめでたく舞を舞う。

簸屑(ひくず)
馬に乗ったり茶を挽いたりすると必ず眠くなる太郎冠者が、簸屑の茶を挽きながら寝込んでしまうので、次郎冠者は懲らしめに鬼の面をかぶせておく・・・。

髭櫓(ひげやぐら)
大嘗会の鉾を持つ役を仰せつかった大髭自慢の夫と、その髭を嫌って剃れという妻の争い。妻は近所の女房どもと語らって攻撃し、夫は髭の周りを櫓で守って防戦するが・・・。

毘沙門連歌(びしゃもんれんが)
二人の参詣人が、鞍馬の毘沙門天の前で連歌を詠むと、毘沙門天が出現し、二人に鉾と鎧兜を授ける。

引敷聟(ひっしきむこ)
聟入りに際し、作法を知らない聟は、いたずらな知人が教えるままに、素襖の上を足にはき、後ろを狩猟の敷物・引敷で隠して出かける。

引括(ひっくくり)
口うるさい女房に離縁を迫るが、代わりにほしい物は何でも持って行けというと女房は袋を持ち出す。その袋に入れたものは・・・。

人を馬(ひとをうま)
大名に言いつけられて太郎冠者が探して連れて帰った新参の者は、人を馬にする特技があるという。そこで冠者が馬になって大名が乗り手になって試みるが・・・。

樋の酒(ひのさけ)
留守番に米蔵を預かった太郎冠者と、酒蔵を預かった次郎冠者。両方の蔵の窓に樋をかけ渡し、酒をそそぎ飲む・・・。

武悪(ぶあく)
不奉公者の武悪を討ち果たせとの主人の厳命を受けた太郎冠者は、友情が先立って武悪を斬ることができず密かに命を助ける。幽霊に化けた武悪は、逆に主人を脅す。

吹取(ふきとり)
ある男が、笛吹きを伴い、五条の橋で妻乞いをする。笛の音に惹かれて現れた女は、笛吹きを夫と思い追いかける。

福の神(ふくのかみ)
神前にぬかずき「福は内」と豆を囃す二人の参詣人の前に、明るい笑い声とともに福の神が出現、富貴繁盛夫婦和合を説いてめでたく舞う。

瓢の神(ふくべのしん)
松尾の末社・瓢の神に力づけられた鉢叩きの太郎は、大勢の仲間と念仏を唱え、空也上人の教えに救われる。

梟山伏(ふくろやまぶし)
山仕事から帰った弟の様子がおかしいので、兄は知り合いの山伏に祈って治療してもらおうとするが、山伏が祈ると弟は奇声を発する。やがて、兄へも感染し・・・。

富士松(ふじまつ)
富士詣から帰った太郎冠者の大事な富士松を手に入れたい主人は、山王の縁日へ行く道すがら、連歌の付け合いをして、何とかせしめようとする。

附子(ぶす)
外出する主人は、太郎冠者と次郎冠者に、桶の中に附子という猛毒が入っているから気をつけろと言い置くが、二人がこわごわふたを取ると、中にはうまそうな黒砂糖があった・・・。

文相撲(ふずもう)
相撲好きな大名は、新参者相手に相撲を取るが、負けた口惜しさから、相撲の指南書を見ながらふたたび組み合う。

無布施経(ふせないきょう)
檀家で読経をすませたが、毎月決まりの布施を主人が出し忘れる。諦めきれない僧は再三小戻りして、説法に事寄せて暗に催促したそのあげく・・・。

二人大名(ふたりだいみょう)
供を連れずに外出した二人の大名が、通りがかりの男に太刀を持たせたばかりにおどされ、身ぐるみはがれた上に、犬・鶏・起き上がり小法師の真似をさせられる。

二人袴(ふたりばかま)
一つの袴を二つに裂き、それぞれ前に当てて舅に挨拶する聟と親。祝言の小舞を所望されて、ついに後姿を見られてしまう。

仏師(ぶっし)
仏像を求めて都に上った田舎者に、仏師と称してすっぱが近づき、前金を取ってから自分が仏像になりすますが・・・。

舟渡聟(ふなわたしむこ)
聟は、聟入りのみやげの酒を矢橋の浦の船頭に飲まれてしまうが、実は、その船頭が訪ねる舅であった・・・。

舟ふな(ふねふな)
遊山に出た主従が川を渡ろうと舟を探すが、「ふね」と呼ぶか「ふな」と呼ぶかで、古歌を引いて言い争う。

文荷(ふみにない)
主人の寵愛する稚児のもとへ恋文を届けるよう言いつけられた太郎・次郎冠者は、文を竹の棒に結びつけ、肩ににない、謡がかりで運ぶ途中、つい封を開き読んでしまう。

文山賊(ふみやまだち)
獲物を逃がした二人の山賊は、喧嘩口論の末、書き置きを残して死のうとするが、妻子のことを思い出して和解する。

文蔵(ぶんぞう)
太郎冠者が都の伯父にふるまわれた温糟粥(うんぞうがゆ)の名が思い出せず、主人は「源平盛衰記」石橋山合戦のくだりを長々と語るはめになる。

法師ヶ母(ほうしがはは)
酒乱の男が妻を追い出すが、子どもが母を恋しがるので、酔いからさめた男は、物狂いの体で市内をさまよい、妻を捜し求める。

棒縛(ぼうしばり)
主人は、自分の留守に召使が盗み酒をしないようにと、太郎冠者の両腕を棒に、次郎冠者を後ろでに縛って出かけるが、両冠者は奇抜な工夫をめぐらして、またしても酒を飲みはじめる・・・。

謀生種(ほうじょうのたね)
伯父の再三のウソ話に、何とか一矢報いようとする甥。しかしウソの種をやろうという伯父に、またもだまされる。

包丁聟(ほうちょうむこ)
聟入りの儀式に際し、前もって作法を記した書物を携えて舅を訪問する聟。まな板と包丁に鯛が出され、料理を所望されるので、かねて用意の書を取り出すと、それは相撲の書だった・・・。

骨皮(ほねかわ)
住持は新発意に寺を譲るにあたり、来訪者への応対の作法を教えるが、その口上を取り違えた新発意は・・・。

盆山(ぼんさん)
盆山の影に隠れた盗人は、その家の主人から、犬だ、猿だとからかわれ、最後には鯛だと言われ、飛び跳ねながら逃げる。

枕物狂(まくらものぐるい)
百歳の祖父が恋わずらいと聞いた二人の孫が心配して本人に真相を尋ねると、初めは恥じて隠していた祖父も、ついに、恋の相手は刑部三郎の娘おとであると告白する・・・。

孫聟(まごむこ)
聟の来訪を迎える舅と太郎冠者は、祖父(舅の父)が出過ぎたふるまいをしないように事前に外出させようと計るが、それを知った祖父は、どうしても聟の前に出たがる。

松囃子(まつばやし)
正月の祝いに門付けをする万歳太郎は、もらう祝儀の多寡で、祝い芸に差をつける。

松脂(まつやに)
正月、弓の弦に張る松脂を煉る行事に、松脂の精が出現し、松脂のめでたいいわれを語って聞かせ、みずから煉り納める。

松楪(まつゆずりは)
丹波の百姓は楪を、津の国の百姓は松を、領主の蔵に納め、年貢によそえた歌を詠み、一つの烏帽子を二人で着て舞を舞う。

鞠座頭(まりざとう)
妙音講を勤めた後、目の見えない匂当たちは、鞠に鈴をつけ、蹴鞠に興ずる。その様子を見た男が、鞠を取って匂当たちをなぶる。

箕被(みかずき)
連歌に熱中して家を顧みない夫に愛想をつかした妻は、離縁のしるしにもらった箕を被いて出ていこうとするが、夫がその後ろ姿を見て発句を詠むと、脇句をつけて和解する。

水掛聟(みずかけむこ)
日照りが続き、隣り合わせに田を所有する聟と舅は、互いに自分の田へ水を引こうとして争い合う。女房は、夫と父の板ばさみになるが、結局は夫に加勢する。

不見不聞(みずきかず)
留守番を頼まれた、耳の遠い太郎冠者と目の不自由な菊市のなぶり合い。

水汲(みずくみ)
野中の清水へ水汲みに来た新発意は、かねて思いを寄せる門前のいちやが濯ぎ物をしているのを見つけ、小歌に託して恋心を訴える。

胸突(むねつき)
金の貸し手に胸を突かれて倒された借り手は、骨が折れたと大げさに痛がりわめき立て、借状を取り戻す。

目近(めちか)
目近・込骨という特殊な扇を買って来いと言いつけられた太郎・次郎冠者は、都のすっぱに騙され、常の扇を売りつけられる。目近とは要のこと、込骨とは骨の数が多いこと。

餅酒(もちざけ)
加賀の百姓は菊酒、越前の百姓は鏡餅を領主の館に納め、年貢によそえた歌や奇抜な歌を詠み、めでたく舞い納める。

貰聟(もらいむこ)
酔いのまぎれに妻を追い出した大酒飲みの夫は、翌日、しおしおと妻の実家を訪ねる。舅はいないとつっぱねるが、妻は夫の声を聞くとたちまち未練が起こる。

八尾(やお)
六道の辻で罪人を待ち受ける閻魔大王の前に現れた亡者は、昔閻魔の稚児だった八尾地蔵からの手紙を差し出す。見れば、信心深いこの亡者を極楽へ送れとの文面。

薬水(やくすい)
美濃の国・本巣の郡に住む祖父が、山奥に湧く不老不死の薬水を飲むと髭も髪も真っ黒になり、腰も伸びる。飲みすぎて赤子に戻ってもいけないと、ほどほどにして帰宅する。

痩松(やせまつ)
丹波の国の山賊が、里帰りの途中の女を襲って持ち物を奪うが、隙を見た女は山賊の長刀を奪って逆襲、持ち物を取り返し身ぐるみをはいでしまう。

八幡前(やはたのまえ)
一芸に秀でた者を聟に取るという有徳人のもとへ聟入り志願の男、弓の名人と触れ込み、放生川で浮き鳥を射損じ、歌を詠んで取り繕うはずが・・・。

祐善(ゆうぜん)
若狭の国の僧が都へ上り、五条の油小路でにわか雨にあい、かたわらの庵に立ち寄ると、生前傘張り職人だった祐善の亡霊が現れ、下手とそしられ狂い死にした顛末を語る。

雪打(ゆきうち)
雪かきをする隣り合わせた若者と百姓が、雪の処分で争うところへ、仲裁に入った老僧。ついで家の中から出てきた若者の母親は、実は老僧が若者の父であると告白して・・・。

弓矢(ゆみや)
和泉の百姓は蓬の矢、河内の百姓は桑の弓を領主の館に納め、それぞれ年貢のめでたいいわれを語り、弓矢の威徳を謡って舞い納める。

弓矢太郎(ゆみやたろう)
天神講の夜、臆病者の太郎の肝試しをしようと講中の者の計略で、太郎を森に行かせ、鬼に化けておどそうとするが、太郎も鬼に化けているので、互いに鬼が出たと勘違いする。

横座(よこざ)
ある男が道で拾った牛の良否を鑑定してもらおうと牛博労に見せると、牛博労は、それは盗まれた自分の牛だと言い、横座という牛の名のいわれを語り、牛に呼びかける・・・。

米市(よねいち)
大晦日。年の瀬を越せない男が、日ごろ目をかけてくれる人から米と小袖を施してもらい、帰って行く。米俵に小袖をかけた姿が、ちょうど女を背負っているように見えるので・・・。

鎧腹巻(よろいはらまき)
鎧腹巻くらべに入用な鎧を求めてくるよう主人に言いつけられた太郎冠者が、都のすっぱにだまされて、鎧について書き集めた反故を売りつけられる。

楽阿弥(らくあみ)
伊勢神宮へ参詣の旅僧が、別保の松原で、たくさんの尺八をつけた一本の松を見つけ、楽阿弥という、非業の死を遂げた尺八吹きの亡霊に出会う。

連歌十徳(れんがじっとく)
連歌十徳の秘事を知った者を抱えようという有徳人のもとへ現れたのは、博奕に食いつめ、衣の十徳を着たにわか出家。

連歌盗人(れんがぬすびと)
連歌の初心講の当番になったが貧乏で催しの準備ができない男は、仲間を語らって盗みを企てる。めざす邸に忍び込むが、座敷の床の懐紙に記された句を読むうちに・・・。

老武者(ろうむしゃ)
曾我の里に住む男が、美しい稚児を連れて鎌倉へ上る途中、藤沢の宿に泊まる。それを聞きつけた近所の若者と祖父とが、稚児をめぐって争奪戦をくりひろげる。

六地蔵(ろくじぞう)
ある田舎者が新築の地蔵堂に六体の地蔵を安置しようと都へ仏師を探しに来る。すっぱは、我こそ安阿弥直系の仏師と偽り、三人の仲間を呼び集めて地蔵に化けさせる。

六人僧(ろくにんそう)
三人連れで諸国仏詣でに出たが、そのうちの一人が他の二人にいたずらで髪を剃られて腹を立て、一人別れて立ち戻り、二人の留守宅を訪れ、その妻たちに両人とも溺死したと報告する。

呂蓮(ろれん)
旅僧がある家に一宿し、説教をすると、主人は感激して仏道修行を志し、その場で剃髪してしまう。配膳に来た妻は驚き怒り、もとのように髪を生やせと僧を痛めつける。

若菜(わかな)
八瀬大原へ同朋のかい阿弥を連れて小鳥を狙いに出た大名が、芝をかざした大原女の一行に出会い、なごやかな野辺の酒宴を楽しむ。 < 詳細解説 >

若和布(わかめ)
寺の改築祝いの酒の肴にワカメを買ってこいと住持に言いつけられた新発意は、都のすっぱにだまされて、若い女を連れて帰る。住持は怒って二人を追い出す。
|
|
 |
|
|
 |
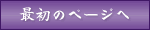 |
 |