|
|
|
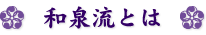 |
 |
いまから569年前、後花園天皇の御代に興り、宗家は当代で20代を数えます。
歌謡的要素が現代的で、叙情性が豊かなことなどが特徴です。
「謡を効果的に取り入れ、都会的に洗練された芸風」との評がありますが、
狂言の型を尊重し、明確で、柔らかみがある都会風の狂言だと言われています。 |
|
 |
 |
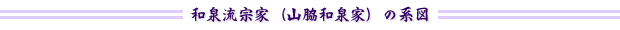 |
 |
 |
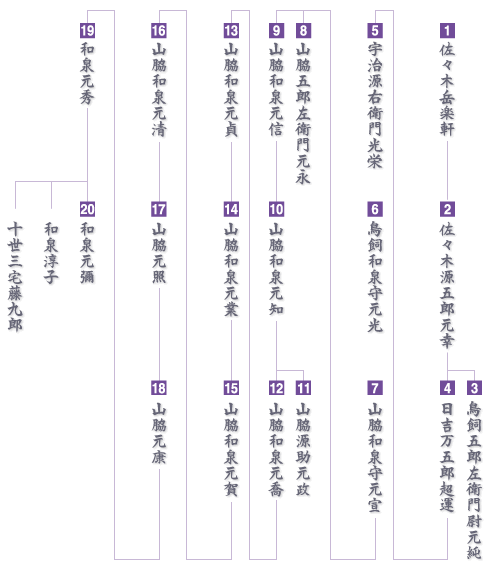 |
|
 |
|
|
 |
和泉流宗家の歴史は、すなわち和泉流の歴史です。
その中で、ある時期に弟子として家を興し、筆頭の職分家となったのが
三宅藤九郎家です。三宅藤九郎家には、宗家家を「師家」と称した古書が
数多く伝承されています。
名前が違っても、時代が流れても同じ心で狂言・和泉流を伝えています。
宗家と責任の重さは違いますが、先人の遺した技と心を守っていく心が、
「三宅藤九郎家」の代を重ね歴史を刻んでいるのです。 |
|
 |
 |
 |
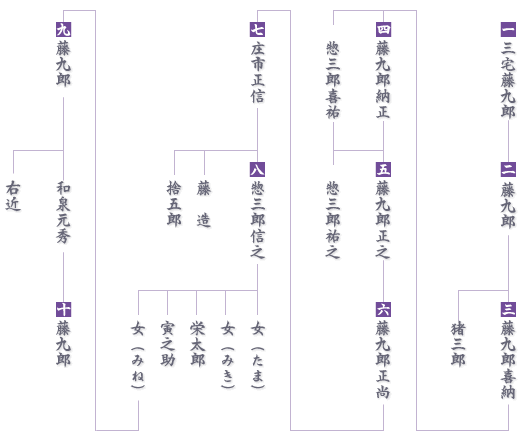 |
|
|
 |
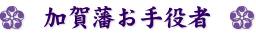 |
 |
流儀の中には、もちろん宗家だけでなく一代で志を立てて入門しプロの狂言師(職分)となる人もいますし、またある時代にそうして職分になった者が代々狂言を生業にして、「家」を認められれば「職分家」と呼ばれるようになります。
その家とともに「芸」と「名前」が受け継がれていくわけですが、三宅藤九郎家は、和泉流職分の筆頭の家格を持ち、古い書物にも「名人・上手」との記載が多く見られる名家といわれています。
江戸時代には加賀藩のお手役者(お抱え⇔そうでない狂言師は町役者と呼ばれる)として、京都と金沢で活躍をしていました。
『金沢の能楽』には、「文化(1800年代)のお手役者」の一覧の中に「三宅藤九郎 小判35両」とあり、当時小判35両をもって召抱えられていたことがわかります。
ある時代に宗家を師として流儀に加わったのが、職分であり職分家です。
三宅藤九郎家もそういった家の一つであり、実際に宗家家を「師家」と称した書物が伝承されています。現在は各家での活動が盛んですし、長い歴史の中では原点を見失いやすいものですが、流儀の歴史を踏まえ、家の歴史を踏まえ、それぞれの「分」を全うするのが職分の真の務めと言えるでしょう。 |
|
 |

寄稿 特別展『三番叟ー喜びありや』パンフレットより
 |

「狂言師・三宅藤九郎」は、和泉流の職分(弟子)家の筆頭として、宗家・山脇和泉家に師事し、藩政期には京住みのまま加賀藩主・前田家の『お手役者』(お抱え狂言師)として代々の藩主、奥方ご観覧の舞台の御用を勤め、また加賀藩ご領地内においても弟子の育成につとめてこられました。
当代の十世・三宅藤九郎師は、祖父である九世・三宅藤九郎師(人間国宝)の指名により、昭和六十三年に名跡を継承、平成元年に国立能楽堂で襲名披露公演を行われました。
平成十年より、演劇の町・能登中島町で「三宅藤九郎お国帰り 狂言和泉流宗家 能登中島公演」を毎年開催しておられます。
特に能登中島は中世、久麻加夫都阿良加志比古神社に所属した幻の猿楽集団「熊木太夫」でも知られるなど、狂言と所縁の深い土地です。
その間、加賀藩祖・前田利家公、お松の方をお祀りする尾山神社「前田利家公御神忌四百年祭」を始め、国指定重要文化財「神門」改修記念祭、お松の方をお祀りする「福寿祭」、また東山鎮座の宇多須神社前田利家公合祀祭など、平成の現在でも「加賀藩お手役者」としてご奉仕されています。
嶽 徹
(財)伝統文化活性化国民協会会員、(財)演劇の町振興事業団主事 | |
|
 |
|
|
 |
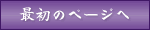 |
 |