|
|
|
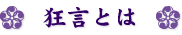 |
 |
|
|
 |
狂言は、今から約600年前、室町時代に成立した、せりふと仕草で演じられる喜劇です。
古典芸能の中で唯一、純粋な喜劇であるだけでなく、日本の芸能の原点とも言われています。
型や伝統を大切に守り伝えられてきましたが、難しい堅苦しいものというわけではありません。
言葉や装束、時代背景は昔のものですが、今でもこういう事はある!こういう人もいる!と
共感して楽しむことができます。
ほのぼのとした中にも鋭い普遍性を持った「笑い」の世界ですから
国内はもちろん、言葉の通じない海外公演でも広く楽しまれ、高い評価を受けています。
2001年には、ユネスコ世界無形(文化)遺産に指定されました。 |
|
 |
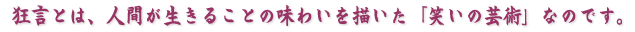 |
 |
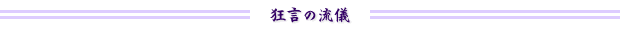 |
|
|
 |
現在、狂言には大蔵流と和泉流の二つの流儀があります。
明治時代までは鷺流という流儀もありましたが、宗家が絶えてしまったため、現在は郷土芸能として山口と佐渡に伝承されています。
それぞれの流儀には宗家家の他にも「職分家」といわれる家があります。
※「職分家」 についてはこちら(三宅藤九郎家)をご覧下さい。
狂言の世界では名取制度はないので、職分であっても全員が「和泉」や「大蔵」と名乗ることはありません。
三宅藤九郎家も、和泉流の筆頭の職分家ですが、苗字は「三宅」です。
普段の公演活動は、各家単位で行われていることが多いので、何流の狂言かということが分かりづらい事もあるようです。 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
和泉流宗家、三宅藤九郎家、野村又三郎家、野村万蔵家、狂言共同社など |
 |
 |
|
大蔵流宗家、茂山家、善竹家、山本東次郎家など |
|
 |
 |
 |
 |
|
| |
|
|
 |
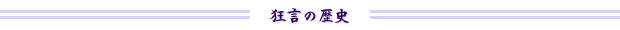 |
 |
奈良時代、中国(当時の唐)から「散楽」という芸能が伝来してきました。
その散楽が日本の風土の中で「猿楽」(または「申楽」)という芸能に発展し、室町時代にこの「猿楽」から今に伝わる「狂言」と「能」の二つの芸能が確立されました。
猿楽本来の滑稽な部分である「本芸」から狂言が、荘厳な部分である「能芸」から能が生まれたといわれています。
基本的に狂言は喜劇、能は悲劇ということができます。 |
|
 |
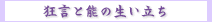 |
 |
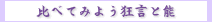 |
 |
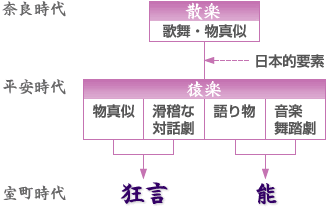 |
 |
| |
狂言 |
能 |
| 内容 |
喜劇 |
悲劇 |
| 上映時間 |
20〜30分/曲 |
1時間〜1.5時間/曲 |
| 登場人物 |
2〜3人 |
10〜20人以上 |
| ことば |
〜でござる
(口語調) |
〜でそうろう
(文語調) |
| 面 |
特別な役だけ着用
(表情豊か) |
シテは必ず着用
(無表情っぽい) |
|
|
|
 |
| 和泉流は流祖佐々木岳楽軒から当代・二十世宗家和泉元彌まで569年の歴史を数えます。 |
 |
|
|
 |
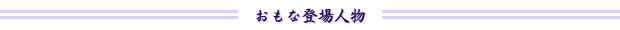 |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
| 狂言を代表する登場人物、と言っても過言ではないでしょう。冠者とは成人男性のことを意味しますが、狂言の太郎冠者といえば召使のこと。怠け者だったり、お酒好きだったり、でも主人想いだったり…とにかく人間味溢れる登場人物です。 |
 |
 |
  |
 |
 |
 |
| 召使だけあって短い袴、そして肩衣と袴の柄も揃っていません。けれどもこの太郎冠者の肩衣は、シンプルな舞台に彩を加え、時には背景の役割を果たすことも。何より狂言の装束の、斬新でダイナミックなデザインを楽しむことができます。ちなみに位の高い男性は上下そろいの柄の装束を身に着けています。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
| 主人のことです。怠け者だったりお酒を飲みすぎたりする太郎冠者を召し使っている苦労がしのばれますが、そこには持ちつ持たれつの信頼関係があるのです。たまに無理難題を言って太郎冠者を困らせるご主人もいます。 |
 |
 |
  |
 |
 |
 |
| 上下そろいの柄の裃です。長い袴をはき、小刀を腰に差しています。太郎冠者と比べると、より高い身分であることが、装束からもわかります。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
| 大名といっても田舎の大名だったり、召使が一人しかいないこともあります。無風流だったり貧乏だったりしますが、それでも大名らしいおおらかさが魅力的です。 |
 |
 |
  |
 |
 |
 |
| 成人男性の正装である素袍裃です。
当然柄も上下揃いで、主と比べると袴に加えて袖も長くなっています。身分が高くなるにつれて、身体を覆う装束も多くなっていきます。頭にかぶっているのは烏帽子(えぼし)といいます。
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
| 一般に山伏と言えば山野で厳しい修行をした僧で、徳が高く、権威の象徴とも言えます。けれども狂言に出てくる山伏は、権威をかさにきて威張っていたり、その割には法力が今ひとつだったりします。 |
 |
 |
  |
 |
 |
 |
| 山野を修行している山伏ですから、動きやすい括り袴に脚半を着けています。また舞台上での歩き方も、「すり足」ではなく「揚げ足」といって足を上げて歩いていきます。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
| 女性が登場する狂言はあまり多くありませんが、出てくる女性は皆たくましく元気です。やきもちを焼いたりだんな様のお尻を叩いて働かせたり、それも夫を思えばこそ…の愛情なのです。 |
 |
 |
  |
 |
 |
 |
女を表す特徴的なものが、頭に巻いている白い布です。女性を表すものですが「美男鬘(びなんかずら)」という名前がついています。
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
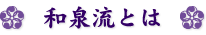 |
 |
いまから567年前、後花園天皇の御代に興り、宗家は当代で20代を数えます。
歌謡的要素が現代的で、叙情性が豊かなことなどが特徴です。
「謡を効果的に取り入れ、都会的に洗練された芸風」との評がありますが、
狂言の型を尊重し、明確で、柔らかみがある都会風の狂言だと言われています。 |
|
 |
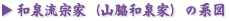 |

|
|
|
 |
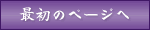 |
 |